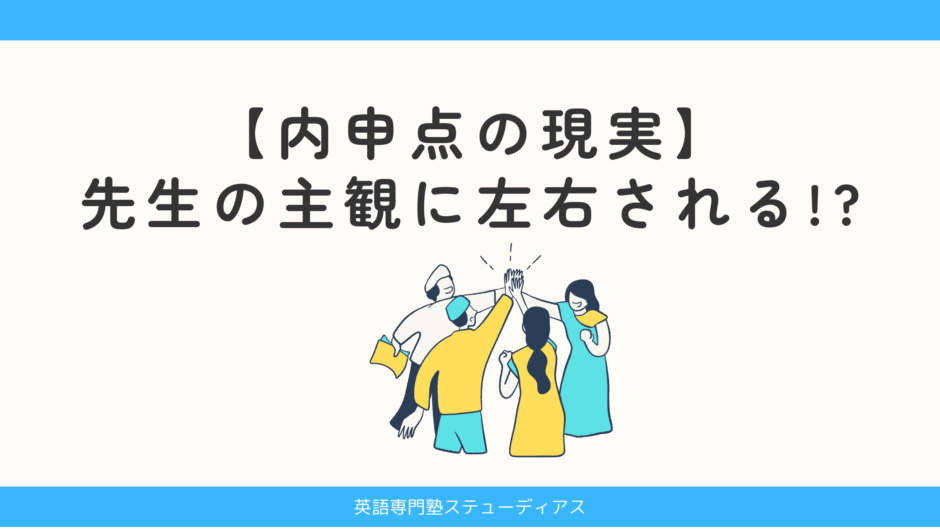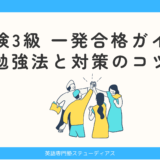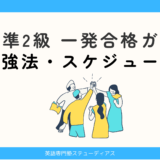皆さん、こんにちは!
成田市の英語専門塾ステューディアスです。
受験が近づくと、保護者の方が気になるのがやっぱり「内申点(通知表の成績)」ですよね。
でも最近、「内申点って先生の主観で決まってない?」「頑張ってるのに評価が低いのはどうして?」というモヤモヤの声を、よく耳にします。
最近Yahoo!ニュースに掲載された記事でも、そうした不満や疑問の声がたくさん取り上げられていました。
今日は「内申点って本当に公平なの?」「じゃあどう向き合えばいいの?」という疑問を、一緒に考えていきたいと思います。
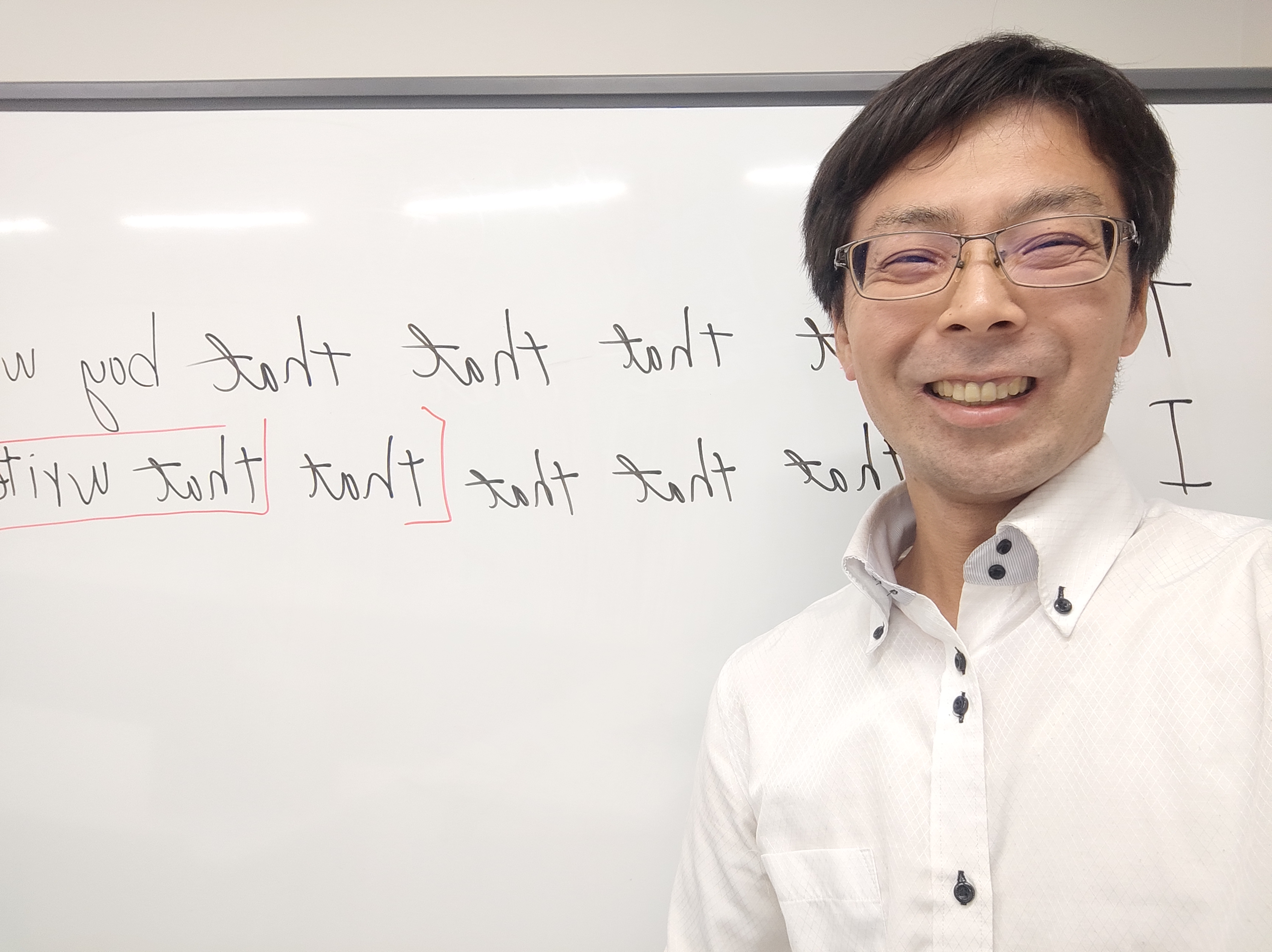
成田市囲護台にある英語専門塾代表
頑張ること、頑張り切ることを伝えています。
Yahoo!ニュースが報じた「評定のばらつき」と内申制度の課題
ネットニュースに載っていた記事はこちらです
https://news.yahoo.co.jp/articles/762fbe0665100a973c68fe51ef4f5ec32675462e?page=1
ネットニュースは消えることが多いので、以下に引用しておきます。
国語は「5」だけど、数学は「1」――など、中学校の教科につけられる「評定」。高校入試の合否に大きく関わる「内申点」にも影響するため、気になっていた人も多いのではないでしょうか。自治体によっては評定の分布を公表していますが、学校ごとに「5」や「1」をつけた割合に大きな差があることが分かりました。成績をつける基準は同じなのに、なぜ差が生まれるのでしょうか。
中学校の内申点は、各教科の評定(最高5~最低1)を足したもので、テストの結果だけでなく、授業態度や課題の提出具合などを加味した上で成績がつけられます。 全国各地の多くの公立高校の入試では、この内申点と学力検査の点数の合計で、合否を決めています。
かつて中学校の内申点は、評定「5」が生徒全体の7%、「4」が24%……と決まった割合でつけられる「相対評価」でした。 ですが、個々の生徒の学力を把握できないといった理由から、今は全国的に、生徒ごとに評価する「絶対評価」で成績がつけるようになりました。
テストの点数はいつも良いのに、5をもらえないとか、一体どうなってるんだ!と親としては苛立つこともあるかと思います。
この記事にはコメント欄もあり、保護者のモヤモヤも率直に書かれていました。
読者コメントから見えてきた「モヤモヤ」
記事には、実際にお子さんを育てている保護者のリアルな声も紹介されていました。その中から、特に印象的だったものを少しご紹介します。
📘 テストの点が良くても評価が上がらない
「うちの子、定期テストでは満点近く取ってるのに、内申は4止まり。
おとなしい性格だから、発言が少ないって理由みたいです…」
🎨 副教科は“好き嫌い”で決まる?
「作品も評価が高くて提出物も完璧。でも『もうちょっとかな』って理由で5がつかない。
発言が多くて目立つ子のほうがいい評価もらってる気がして…」
😓 面談で言ったら突然オール5に?
「保護者会で『評価が下がって子どもが落ち込んでいる』と話したら、次の成績で急に全部5に。
正直ちょっと…不信感が残りました。」
こうした声から見えてくるのは、「何を基準に成績が決まっているのかが見えづらい」という不安と、
「先生のさじ加減ひとつで子どもの進路が決まってしまうのは納得できない」という感情からだと思います。
そもそも成績って、どうやってつけられているの?
Benesseの進学情報サイトによると、中学校の成績(評定)は、次の3つの観点でつけられているそうです:
- 知識・技能(=テストや単語、計算などの基礎力)
- 思考・判断・表現(=自分の考えを持って答えられるか)
- 主体的に学習に取り組む態度(=授業態度、振り返り、提出物など)
このうち、特にモヤモヤの原因になりやすいのが「主体的に〜」の部分。
授業中に手を挙げる、先生の問いに反応する、ノートを丁寧に書く、提出物に自分の意見をしっかり書く…。
こういった“姿勢”が見られているようです。
でもこれ、どうしても先生の見え方・感じ方に左右されるので、「主観的になりがち」だと言われています。
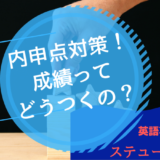 【内申点UPのポイント】相対評価?絶対評価?今の成績の付け方を理解しておこう
【内申点UPのポイント】相対評価?絶対評価?今の成績の付け方を理解しておこう 私の意見:評価の“理不尽さ”も、ある意味残酷な「社会の予行演習」
こうして見てくると、「結局、先生の主観じゃん!」とガッカリしてしまうお気持ち、すごくよく分かります。
私もこの親として納得できない日もきっと来ると思います。
でも、私自身はこうも考えています。
社会に出ても、完全に公平な評価なんてほとんどない。
職場でも、上司に好かれている人の意見が通ったり、声が大きいばかり評価されたり。
「いつも正当に評価される」なんて理想にすぎません。
そう考えると、今の学校での内申制度も、“理不尽に感じることがあっても、自分の立ち回り方を学ぶ場”と捉えることもできると思うのです。
「評価されるにはどうしたらいいか」を考える習慣をつけることが、将来、理不尽なことにも折れずに乗り越えていける“強さ”につながっていくのではないかと思っています。
例えば「上司は自分に何を期待しているのか?」とか「お客さんに喜んでもらうにはどうしたらいいのか?」そんな思考訓練の場と捉えられないだろうかという提案です。
もちろん、悔しい思いや納得いかない気持ちになる子もたくさんいます。
だからこそ、私たち大人ができるのは、「どうしてこうなったのか」「これからどうすればよいか」を一緒に考え、子どもの気持ちに寄り添って、前を向けるように支えることなんだと思います。
正直なところ、今の内申制度には改善すべき点がたくさんあります。
でも、制度が変わることを祈るくらいだったら、自分ができることを考えてほしいと思うわけです。
これも不当な評価を受けている生徒さんとその保護者にとってはキレイごとに聞こえるかもしれませんね。
ちょっと感情的になってしまったかもしれませんが、それだけ内申点について思うところがある、ということで……。今日はこの辺で終わります。
最後までお読みいただき、本当にありがとうございました!